2016年日本朱子学研究综述
| 内容出处: | 《朱子学年鉴.2016》 图书 |
| 唯一号: | 130820020230002330 |
| 颗粒名称: | 2016年日本朱子学研究综述 |
| 分类号: | B244.7 |
| 页数: | 6 |
| 页码: | 170-175 |
| 摘要: | 本文记述了2016年日本朱子学研究会的成立以及发展。 |
| 关键词: | 2016年 日本朱子学 研究综述 |
内容
一、日本儒教学会の設立
本年の日本儒教研究を特徴づける出来事としては、何よりもまず、日本儒教学会の設立を挙げなくてはならない。日本を代表する儒教研究者たちが 発起人となり、2016年5月14日に東洋文庫(東京都文京区)でその創立大会が行われた。東洋文庫は世界有数、そして日本随一の「東洋学」の研究図書館であり、「詩有六義」(「毛詩大序」)から名を取った名庭園「六義園」の近傍に立地している。日本儒教研究の一つの出発を記念するのに相応しい場 所である。
設立大会ではまず、発起人代表で、ある土田健次郎(早稲田大学教授)による開会挨拶が行われた。その内容のうちに、学会設立趣旨の大概は尽くさ れていた。土田は次のような内容を述べた。すなわち、現在の日本には儒教の専門学会が存在せず、儒教の研究は主に中国文化学会•日本思想史学会な ど、諸学会で分散して行われている。これは奇妙なことである。他のアジア 発の諸教諸学、すなわち仏教や道教については印度哲学学会や日本道教学 会がすでに存在するのに、なぜ儒教についてのみ存在しないのか。この事情 は海外の儒教研究者からも驚きをもって指摘されることであり、かつ近年増加•進展している海外研究者との共同研究カヾ、個人単位の散発的で小規模のものにとどまりがちであることの要因ともなっている。そこで日本の儒教研 究者の恒常的な交流の場として、ならびに国際学術交流の基盤として、本学会を設立したい[1]。土田の発言の更概は以上であった。
その後、ちょうど東洋文庫を来訪中であった中華人民共和国の程永華•駐日大使が祝辞を述べられた。続いてシンポジウム「日本における儒教 研究の現在」が行われ、各地域各時代の儒教研究の第一人者が報告と討論を行なった。担当者は次のようである。日本近世儒教:前田勉(愛知教育大学教授)、日本近代儒教:河野有理(首都大学東京准教授)、朝鮮儒教:山内弘一(上智大学教授)、中国古代儒教:渡邊義浩(早稲田大学教授)、中国近世儒教:小島毅(東京大学教授)、中国現代儒教:中島隆博(東京大学教授)。上の担当範囲に瞭然な通り、本学会は「日本の儒教」についての学会ではなく、日本の研究者を中心とする「儒教の学会」である。とはいえ、本学会は日本思想史学会と並んで「日本の儒教」の一大研究中心となってゆくことカヾ、極めて高い蓋然性をもって予想される。日本朱子学に関連する限りで登壇者たちの報告内容を紹介すると、次のようである⑵。まず前田勉は日本思想史研究の中で近世儒教研究の位置と量とが相対的に低下していることへの「一種の危機感」のもと、丸山真男•尾藤正英•渡辺浩らによる戦後の日本儒教研究の方法論や研究視角を総括し、その上で近世後期に見られる「会読」の慣習の中で日本近代を担う選良たちの気風が涵養されたことを後付けた。その気風は、これまで戦後日本で声高に提唱され、模索された西欧近代型の「主体性」とは異なるアジア的な「もう一つの近代」の所在を示していると前 田は示唆する。また河野有理は、田口卯吉(1855-1905 )や加藤弘之(1836-1916)ら近代日本の代表的な知識人たちか、、「封建」「郡県」という儒教の古典的な語彙を用いて、地方分権や立憲政体をめぐる同時代的な議論を展開していることを紹介し、近代日本においても「語彙データベース」として儒教が有為に機能していたことを示した。またその後の総合討論においては登壇者相互、また参加した学会員たちによる活発な議論が交わされたが、報告者(板東)の印象に残ったのは、多くの発言者が、、他の儒教文化圏における儒教 研究が、もつ熱気や現代性に対して、日本人研究者はあくまで「過去のもの」 として客観的に儒教を研究しているという「温度差」や「対象との距離」を強調し、かつそれを日本の研究者の特色として肯定的に評価していた点であ った。
その後、総会にて土田健次郎が初代会長、前田勉が副会長を務めることが決議された。同時に任命された理事及び評議員には、日本の代表的な儒教研究者が名を連ねた。上記の土田の提言の通り、日本の儒教研究者の総合的な交流の場が設けられたことは極めて意義深く、かつ儒教に関する国際的な共同研究の主体としても本会が大きな役割を果たしてゆくことが期待される。
二、日本人の死生観と朱子学
人は死んだ後、どこへ行くのか。天国•極楽浄土•地獄のような他界に赴くのか、それとも神的な存在となって現世に留まるのかあるいは近代の「科学的」世界観が説く如く、消滅してそれきりなのか。そして、こうした死後の世界の構想は、この生をいかに生きるかという問いへと連動してくる。このような死と生との捉え方を、日本では多く「死生観」とよぶ・。日本の思想文化全体と同じく、日本人の死生観もまた、良くいえば重層的であり、悪くいえば極めて曖昧である。古代神話における死者の国(黄泉国)への恐れや、平安時代における浄土教系仏教の流行など、、日本人の死生観は時代ごとに極めて異なった姿を見せるが、今日の日本人の平均的な死生観を決定づけた最も重要な契機は、やはり江戸時代における徳川幕府による全国民への仏教の強制である。これにより日本人の死に関する儀礼(葬・祭)は仏教式で行われることになった。幕府が瓦解し、信教の自由が認められた近現代でもなお、大多数の日本人の葬祭は仏教式である。ならば徳川時代以降、日本人の死生観は仏教一色に塗りつぶされてしまったのか。そうではない。日本人の習俗を調査し、日本民俗学の基礎を築いた柳田國男(1875~1962)⑶は、大半の日本人は形式的には仏教の葬送儀礼を受容しつつも、観念の上では輪廻や極楽往生といった仏教の一般的な死後観を承認していないと主張した(『先祖の話』1946)〇柳田によれは,、日本の「常民」(農村で稲作を営む平均的な日本人)の死生観は、死後も神として現世にとどまり、子孫の祭りに応じて定期的に来臨し、いつまでも子孫を見守り続けるというものである。ここでは死者は輪廻することも成仏することもな・い。こうした柳田の説に対しては、仏教は日本人の死生観と葬祭とに決定的な影響を及ぼしているという反論もあり⑷、充分な結論が得られていないのが現状である。
そして如上の死生観は、日本において極めて現代的な問題と化している。大家族から核家族(単婚小家族)への急速な移行や、長引く不況による世帯年収の減少は、家族単位で営まれる葬儀の形を抜本的に変えつつある。伝統的な仏式葬儀の虚飾を批判する宗教学者•島田裕巳の『葬式は、要らない』(幻冬舎、2010)というセンセーシ크ナルな書籍が大きな反響を呼び、仏式の葬儀に代わってキリスト教式•神道式•無宗教式といった新しい形式の葬儀が増加しつつある(総体的に見ると薄葬化の傾向が著しい)。大手スーパーの葬儀業界への参入や、国際的な通信販売会社による葬儀への「僧侶派遣」事業の開始も、葬儀の商業化•形式化として深刻に受け止められた。またさらに、国際問題として焦点化して久しい靖国神社も、“国に殉じた大を神として祀る”という一定の死生観にもとづいた施設であって、それが日本人の伝統的な死生観からして自然なものであるのか、それとも近代に入ってから作為されたイデオロギーに過ぎないのかという問題が、識者たちの論戦の重要な一論点を構成している。
で、は、このように錯綜し、かつアクチ그アルな日本人の死生観に対して、朱子学はどのような影響を及ぼしたのか。ここまでの概略に瞭然な通り、“日本人の死生観”を論じる際に言及される二大因子は仏教と神道(基層信仰)であって、朱子学ではな・い。それゆえ日本人の死生観と朱子学との関わりについては従来、十分な顧慮が払われていなかったのである。しかるに本年、この関わりを後付けた労作が上梓された。本村昌文『今を生きる江戸思想一十七世紀における仏教批判と死生観』(ぺりかん社、2016.9)である。徳川幕府の統治はちょうど17世紀の初頭(1603)にはじまり、前述の通り公の宗教政策としては仏教が行われたが、開幕とともに活動を開始した儒者たちは、彼らが尊崇し、依拠した宋学者たちに倣って仏教批判を展開した。彼らの仏教批判は、一般に朱熹たちの排仏言説の単なる「焼き直し」「受け売り」にすぎないといわれ、概して独創性に乏しいものとされる。しかし本村は、17世紀の日本儒者たちの著作を丁寧に検討し、そこに日本儒者独自の思惟と意義とを見出している。本著で扱われるのは、中江藤樹(1608~1648)、林羅山(1583~1657)、松永尺五(1592~1657)、清水春流(1626~?)、向井元升(1609~1677)、熊沢蕃山(1619~1691)、中村惕斎(1629~1702)といった有名無名の儒者たちの専門的な著作と、「仮名草子」とよばれる一般大衆向けの啓蒙書とである(漢文の読解能力が僧侶や儒者のみに限定されていた近世前期社会にあって、仮名で書かれ、内容も平易で通俗的な仮名草子は、かえって本格的な漢文儒書以上の社会的な影響力を有していた)。本村によると、これら十七世紀の儒教文献の中には、1640年頃を境にして、大きな変化が認められるという。すなわち、17世紀前半の儒者は、人間の死後の問題にはほとんど言及することなく、“仏教は倫常道徳を解体する「異端」の教えであり、現世の人倫を成立させる教えとしては儒教が最勝である”という、韓愈以来の排仏言説の常套形を用いて仏教を批判した。このように「いまをいかに生きるか」(p.51)という関心に集中した儒教教説を、本村は〈生の教説〉と呼ぶ。しかし十七世紀の半ば以降になると、儒者たちは仏教の輪廻や極楽往生の説を批判し、気の聚散や鬼神の来格を説いて、積極的に朱子学に基つ’く死後の世界を語り始める。これを本村は〈生死の教説〉と呼んでいる。このように1640年頃を境として、〈生の教説〉から〈生死の教説〉への移行が見られると本村は結論づけるのである。それが開幕後半世紀ほどのタイミングで生じた理由については、戦乱の終息と社会の安定の中で、一つには「キリスト教や異国の宗教に惑わぬように人びとを教化するという意識」(p.291)が儒者たちに目覚めたためであり、もう一つには「人々が死後
のことに不安や恐れを抱き、また死生の根幹を理解していないという認識」(p.292)が生じたためと分析されている。安定と平和を取り戻した社会の中 で、公権力によって強制された仏教的死生観を越えた死生観が模索され、朱子学の教説が大きな存在感をもったのである。
本村によると、当時の日本人儒者が朱子学の死生観の根本典拠として繰り返し参照したのは、死後の気/魂魄の聚散や、同一気の子孫の祭祀による感格を説く『朱子語類』巻三•第十九条である。ここで日本儒者の死生観が朱子の「受け売り」に留まらないのは、日本儒者たちが朱子の議論の中で“気の散逸”を意図的に捨象し、むしろ“死後の霊魂の不滅”を強調してゆく点である。道徳的に律された生を生きた人は、死後も消滅することなく、超越的な存在としてこの世界に留まり、とりわけその本性は子々孫々に無窮に受け継がれてゆく。朱子の議論から日本人が読み出したこうした死生観は、神道の語彙や概念と混淆してゆく。本村は本書終章で、同じく17世紀半ばに仏教とは異なる死生観を語り出した神道家•吉川惟足(1616~1694)の死生観を取り上げ、、それが朱子学ではな、く「神避」「長隠」「日少宮」など神道の語彙を用いて語られたものでありなが、ら、「使用するタームは異なるものの、死後の霊魂がどこかへ回帰し永続するという思考の枠組みは、本書で検討してきた十七世紀中葉において形成された朱子学をベースとした死生観にも共通する」(p.293)と指摘している⑶。すでに瞭然であるカヾ、こうした死生観は、柳田が分析した日本人の民俗的死生観とも極めて似通っているのである。「日本人固有」とされ、「神道的」とされる死生観と、朱子学の死生観との思想的な交渉過程については、これからの日本朱子学研究の一大テーマとなるであろう。
なお、本村の著作は死生観についての書物の上に記された教說を分析したものであり、死生観が具体的に実践される儀ネ.Lの上までは及んでいない。本村が教說の上での転機とした1640年からおよそ30年遅れて、1670年頃に、儀礼の上での儒教的死生観の転機が訪れる。日本の先進的な政治家や儒者たちによって、『朱子家礼』に基づいた実際の儒葬が試行され始めるのである(その大半は幕府の禁圧によって頓挫した)。まず寛文12(1672)年に会津藩主・保科正之(1611~1672)の儒葬が幕府の抵抗を押し切る形で斎行され、続いて天和2(1682)年には日本随一の淳儒•山崎闇斎(1618~1682)の儒葬があり、遅れて元禄13(1700)年には朱舜水(1600~1682)を賓師とした水戸藩主•徳川光囹(1628~1700)の儒葬が行われた。こうした儀礼としての儒葬については、2012年の本稿で紹介した田世民『近世日本における儒礼受容の研究』(ぺりかん社、2012)がある。こちらの儀礼面でもやはり、朱子学式の葬儀が次第に国粋意識の高まりとともに神道式の葬儀へと換骨奪胎されてゆく過程が見られる⑹のが極めて興味深〉ゝ。
(作者单位:日本皇学馆大学)
本年の日本儒教研究を特徴づける出来事としては、何よりもまず、日本儒教学会の設立を挙げなくてはならない。日本を代表する儒教研究者たちが 発起人となり、2016年5月14日に東洋文庫(東京都文京区)でその創立大会が行われた。東洋文庫は世界有数、そして日本随一の「東洋学」の研究図書館であり、「詩有六義」(「毛詩大序」)から名を取った名庭園「六義園」の近傍に立地している。日本儒教研究の一つの出発を記念するのに相応しい場 所である。
設立大会ではまず、発起人代表で、ある土田健次郎(早稲田大学教授)による開会挨拶が行われた。その内容のうちに、学会設立趣旨の大概は尽くさ れていた。土田は次のような内容を述べた。すなわち、現在の日本には儒教の専門学会が存在せず、儒教の研究は主に中国文化学会•日本思想史学会な ど、諸学会で分散して行われている。これは奇妙なことである。他のアジア 発の諸教諸学、すなわち仏教や道教については印度哲学学会や日本道教学 会がすでに存在するのに、なぜ儒教についてのみ存在しないのか。この事情 は海外の儒教研究者からも驚きをもって指摘されることであり、かつ近年増加•進展している海外研究者との共同研究カヾ、個人単位の散発的で小規模のものにとどまりがちであることの要因ともなっている。そこで日本の儒教研 究者の恒常的な交流の場として、ならびに国際学術交流の基盤として、本学会を設立したい[1]。土田の発言の更概は以上であった。
その後、ちょうど東洋文庫を来訪中であった中華人民共和国の程永華•駐日大使が祝辞を述べられた。続いてシンポジウム「日本における儒教 研究の現在」が行われ、各地域各時代の儒教研究の第一人者が報告と討論を行なった。担当者は次のようである。日本近世儒教:前田勉(愛知教育大学教授)、日本近代儒教:河野有理(首都大学東京准教授)、朝鮮儒教:山内弘一(上智大学教授)、中国古代儒教:渡邊義浩(早稲田大学教授)、中国近世儒教:小島毅(東京大学教授)、中国現代儒教:中島隆博(東京大学教授)。上の担当範囲に瞭然な通り、本学会は「日本の儒教」についての学会ではなく、日本の研究者を中心とする「儒教の学会」である。とはいえ、本学会は日本思想史学会と並んで「日本の儒教」の一大研究中心となってゆくことカヾ、極めて高い蓋然性をもって予想される。日本朱子学に関連する限りで登壇者たちの報告内容を紹介すると、次のようである⑵。まず前田勉は日本思想史研究の中で近世儒教研究の位置と量とが相対的に低下していることへの「一種の危機感」のもと、丸山真男•尾藤正英•渡辺浩らによる戦後の日本儒教研究の方法論や研究視角を総括し、その上で近世後期に見られる「会読」の慣習の中で日本近代を担う選良たちの気風が涵養されたことを後付けた。その気風は、これまで戦後日本で声高に提唱され、模索された西欧近代型の「主体性」とは異なるアジア的な「もう一つの近代」の所在を示していると前 田は示唆する。また河野有理は、田口卯吉(1855-1905 )や加藤弘之(1836-1916)ら近代日本の代表的な知識人たちか、、「封建」「郡県」という儒教の古典的な語彙を用いて、地方分権や立憲政体をめぐる同時代的な議論を展開していることを紹介し、近代日本においても「語彙データベース」として儒教が有為に機能していたことを示した。またその後の総合討論においては登壇者相互、また参加した学会員たちによる活発な議論が交わされたが、報告者(板東)の印象に残ったのは、多くの発言者が、、他の儒教文化圏における儒教 研究が、もつ熱気や現代性に対して、日本人研究者はあくまで「過去のもの」 として客観的に儒教を研究しているという「温度差」や「対象との距離」を強調し、かつそれを日本の研究者の特色として肯定的に評価していた点であ った。
その後、総会にて土田健次郎が初代会長、前田勉が副会長を務めることが決議された。同時に任命された理事及び評議員には、日本の代表的な儒教研究者が名を連ねた。上記の土田の提言の通り、日本の儒教研究者の総合的な交流の場が設けられたことは極めて意義深く、かつ儒教に関する国際的な共同研究の主体としても本会が大きな役割を果たしてゆくことが期待される。
二、日本人の死生観と朱子学
人は死んだ後、どこへ行くのか。天国•極楽浄土•地獄のような他界に赴くのか、それとも神的な存在となって現世に留まるのかあるいは近代の「科学的」世界観が説く如く、消滅してそれきりなのか。そして、こうした死後の世界の構想は、この生をいかに生きるかという問いへと連動してくる。このような死と生との捉え方を、日本では多く「死生観」とよぶ・。日本の思想文化全体と同じく、日本人の死生観もまた、良くいえば重層的であり、悪くいえば極めて曖昧である。古代神話における死者の国(黄泉国)への恐れや、平安時代における浄土教系仏教の流行など、、日本人の死生観は時代ごとに極めて異なった姿を見せるが、今日の日本人の平均的な死生観を決定づけた最も重要な契機は、やはり江戸時代における徳川幕府による全国民への仏教の強制である。これにより日本人の死に関する儀礼(葬・祭)は仏教式で行われることになった。幕府が瓦解し、信教の自由が認められた近現代でもなお、大多数の日本人の葬祭は仏教式である。ならば徳川時代以降、日本人の死生観は仏教一色に塗りつぶされてしまったのか。そうではない。日本人の習俗を調査し、日本民俗学の基礎を築いた柳田國男(1875~1962)⑶は、大半の日本人は形式的には仏教の葬送儀礼を受容しつつも、観念の上では輪廻や極楽往生といった仏教の一般的な死後観を承認していないと主張した(『先祖の話』1946)〇柳田によれは,、日本の「常民」(農村で稲作を営む平均的な日本人)の死生観は、死後も神として現世にとどまり、子孫の祭りに応じて定期的に来臨し、いつまでも子孫を見守り続けるというものである。ここでは死者は輪廻することも成仏することもな・い。こうした柳田の説に対しては、仏教は日本人の死生観と葬祭とに決定的な影響を及ぼしているという反論もあり⑷、充分な結論が得られていないのが現状である。
そして如上の死生観は、日本において極めて現代的な問題と化している。大家族から核家族(単婚小家族)への急速な移行や、長引く不況による世帯年収の減少は、家族単位で営まれる葬儀の形を抜本的に変えつつある。伝統的な仏式葬儀の虚飾を批判する宗教学者•島田裕巳の『葬式は、要らない』(幻冬舎、2010)というセンセーシ크ナルな書籍が大きな反響を呼び、仏式の葬儀に代わってキリスト教式•神道式•無宗教式といった新しい形式の葬儀が増加しつつある(総体的に見ると薄葬化の傾向が著しい)。大手スーパーの葬儀業界への参入や、国際的な通信販売会社による葬儀への「僧侶派遣」事業の開始も、葬儀の商業化•形式化として深刻に受け止められた。またさらに、国際問題として焦点化して久しい靖国神社も、“国に殉じた大を神として祀る”という一定の死生観にもとづいた施設であって、それが日本人の伝統的な死生観からして自然なものであるのか、それとも近代に入ってから作為されたイデオロギーに過ぎないのかという問題が、識者たちの論戦の重要な一論点を構成している。
で、は、このように錯綜し、かつアクチ그アルな日本人の死生観に対して、朱子学はどのような影響を及ぼしたのか。ここまでの概略に瞭然な通り、“日本人の死生観”を論じる際に言及される二大因子は仏教と神道(基層信仰)であって、朱子学ではな・い。それゆえ日本人の死生観と朱子学との関わりについては従来、十分な顧慮が払われていなかったのである。しかるに本年、この関わりを後付けた労作が上梓された。本村昌文『今を生きる江戸思想一十七世紀における仏教批判と死生観』(ぺりかん社、2016.9)である。徳川幕府の統治はちょうど17世紀の初頭(1603)にはじまり、前述の通り公の宗教政策としては仏教が行われたが、開幕とともに活動を開始した儒者たちは、彼らが尊崇し、依拠した宋学者たちに倣って仏教批判を展開した。彼らの仏教批判は、一般に朱熹たちの排仏言説の単なる「焼き直し」「受け売り」にすぎないといわれ、概して独創性に乏しいものとされる。しかし本村は、17世紀の日本儒者たちの著作を丁寧に検討し、そこに日本儒者独自の思惟と意義とを見出している。本著で扱われるのは、中江藤樹(1608~1648)、林羅山(1583~1657)、松永尺五(1592~1657)、清水春流(1626~?)、向井元升(1609~1677)、熊沢蕃山(1619~1691)、中村惕斎(1629~1702)といった有名無名の儒者たちの専門的な著作と、「仮名草子」とよばれる一般大衆向けの啓蒙書とである(漢文の読解能力が僧侶や儒者のみに限定されていた近世前期社会にあって、仮名で書かれ、内容も平易で通俗的な仮名草子は、かえって本格的な漢文儒書以上の社会的な影響力を有していた)。本村によると、これら十七世紀の儒教文献の中には、1640年頃を境にして、大きな変化が認められるという。すなわち、17世紀前半の儒者は、人間の死後の問題にはほとんど言及することなく、“仏教は倫常道徳を解体する「異端」の教えであり、現世の人倫を成立させる教えとしては儒教が最勝である”という、韓愈以来の排仏言説の常套形を用いて仏教を批判した。このように「いまをいかに生きるか」(p.51)という関心に集中した儒教教説を、本村は〈生の教説〉と呼ぶ。しかし十七世紀の半ば以降になると、儒者たちは仏教の輪廻や極楽往生の説を批判し、気の聚散や鬼神の来格を説いて、積極的に朱子学に基つ’く死後の世界を語り始める。これを本村は〈生死の教説〉と呼んでいる。このように1640年頃を境として、〈生の教説〉から〈生死の教説〉への移行が見られると本村は結論づけるのである。それが開幕後半世紀ほどのタイミングで生じた理由については、戦乱の終息と社会の安定の中で、一つには「キリスト教や異国の宗教に惑わぬように人びとを教化するという意識」(p.291)が儒者たちに目覚めたためであり、もう一つには「人々が死後
のことに不安や恐れを抱き、また死生の根幹を理解していないという認識」(p.292)が生じたためと分析されている。安定と平和を取り戻した社会の中 で、公権力によって強制された仏教的死生観を越えた死生観が模索され、朱子学の教説が大きな存在感をもったのである。
本村によると、当時の日本人儒者が朱子学の死生観の根本典拠として繰り返し参照したのは、死後の気/魂魄の聚散や、同一気の子孫の祭祀による感格を説く『朱子語類』巻三•第十九条である。ここで日本儒者の死生観が朱子の「受け売り」に留まらないのは、日本儒者たちが朱子の議論の中で“気の散逸”を意図的に捨象し、むしろ“死後の霊魂の不滅”を強調してゆく点である。道徳的に律された生を生きた人は、死後も消滅することなく、超越的な存在としてこの世界に留まり、とりわけその本性は子々孫々に無窮に受け継がれてゆく。朱子の議論から日本人が読み出したこうした死生観は、神道の語彙や概念と混淆してゆく。本村は本書終章で、同じく17世紀半ばに仏教とは異なる死生観を語り出した神道家•吉川惟足(1616~1694)の死生観を取り上げ、、それが朱子学ではな、く「神避」「長隠」「日少宮」など神道の語彙を用いて語られたものでありなが、ら、「使用するタームは異なるものの、死後の霊魂がどこかへ回帰し永続するという思考の枠組みは、本書で検討してきた十七世紀中葉において形成された朱子学をベースとした死生観にも共通する」(p.293)と指摘している⑶。すでに瞭然であるカヾ、こうした死生観は、柳田が分析した日本人の民俗的死生観とも極めて似通っているのである。「日本人固有」とされ、「神道的」とされる死生観と、朱子学の死生観との思想的な交渉過程については、これからの日本朱子学研究の一大テーマとなるであろう。
なお、本村の著作は死生観についての書物の上に記された教說を分析したものであり、死生観が具体的に実践される儀ネ.Lの上までは及んでいない。本村が教說の上での転機とした1640年からおよそ30年遅れて、1670年頃に、儀礼の上での儒教的死生観の転機が訪れる。日本の先進的な政治家や儒者たちによって、『朱子家礼』に基づいた実際の儒葬が試行され始めるのである(その大半は幕府の禁圧によって頓挫した)。まず寛文12(1672)年に会津藩主・保科正之(1611~1672)の儒葬が幕府の抵抗を押し切る形で斎行され、続いて天和2(1682)年には日本随一の淳儒•山崎闇斎(1618~1682)の儒葬があり、遅れて元禄13(1700)年には朱舜水(1600~1682)を賓師とした水戸藩主•徳川光囹(1628~1700)の儒葬が行われた。こうした儀礼としての儒葬については、2012年の本稿で紹介した田世民『近世日本における儒礼受容の研究』(ぺりかん社、2012)がある。こちらの儀礼面でもやはり、朱子学式の葬儀が次第に国粋意識の高まりとともに神道式の葬儀へと換骨奪胎されてゆく過程が見られる⑹のが極めて興味深〉ゝ。
(作者单位:日本皇学馆大学)
知识出处
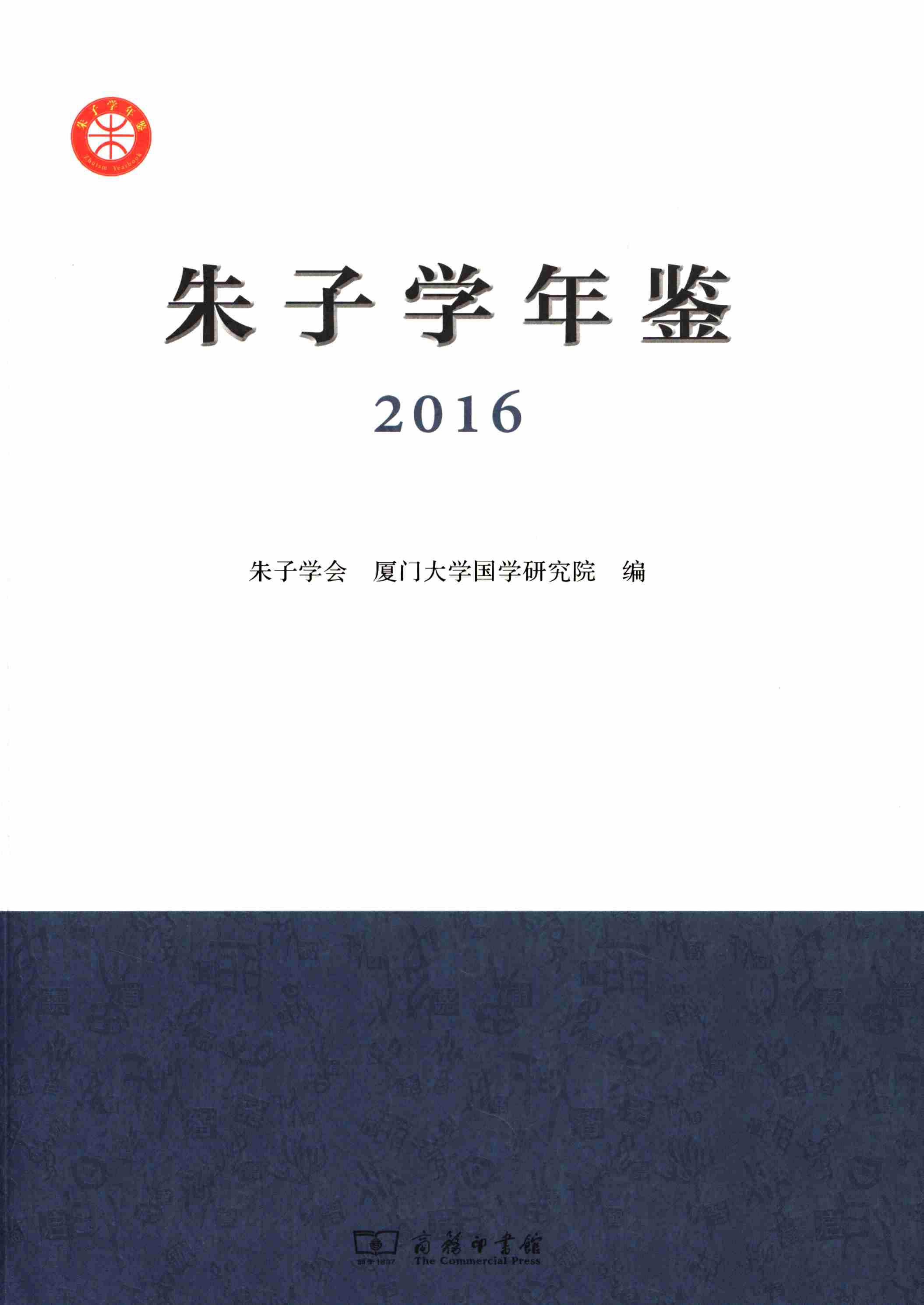
《朱子学年鉴.2016》
出版者:商务印书馆
本年鉴内容设特稿、朱子学研究新视野、全球朱子学研究述评、朱子学书评、朱子学研究论著、朱子学研究硕博士论文荟萃、朱子学界概况、朱子学学术动态、资料辑要9个栏目。
阅读
相关人物
板东洋介
责任者